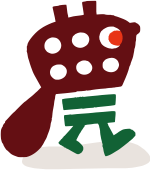丁寧に荷づくりされたおいしいお野菜はお客様からも大人気!真っ直ぐ仕事に向き合う農家さんです。
日野市万願寺で300年以上続く農家の11代目・篠崎好雅さん。
学生時代には一度学芸員を志すも、幼い頃から農業が身近にあり、代々続いてきた土地を無駄にしたくないという思いから農業の道へ進まれました。
今では、毎年2月から5月にかけて入荷する芳醇な香りを放つイチゴが代名詞ともいえる篠崎さんに、イチゴの栽培についてお話を伺いました。
栽培を始めてからこれまで
2005年、イチゴの栽培を開始するためにハウスを建設。最初の頃はマニュアルを読みながら始めるも、やっとの思いで育ったイチゴは甘みがなく色も黒っぽくなってしまったのだとか。
その後は、栽培期間中小まめに糖度を測りながら試行錯誤を繰り返していき、今では毎年天候やハウスの様子をよく観察し細やかな調整を欠かしません。
毎日専用の機械で行う水やりでは、規定量よりも水分量を少なくすることで味の濃いイチゴに育てる工夫も。
話を伺いながらハウスを見渡すと、大小さまざまなイチゴが実っていました。

この大きさの違いは花にあります!「あれは大きいですよ」と見せていただいたのは、たくさんの花びらが重なる花。
今シーズン最も早く、11月末に咲いた花は、このように大きい花が多いそうです。ここから小さな実ができて、完熟するまでには一ヶ月半ほどかかります。

香るイチゴを育てるには
おいしいイチゴは徹底した温度管理によって生まれます。
全部で3,000ほどの苗のうち、ハウス中央部には赤く色づいたイチゴが、ハウスの端にはこれから色づくであろうイチゴが多く実り、同じハウスの中でも外気との距離による違いが見られました。
篠崎さんは、「温度を上げるのは簡単だけど、下げるのは大変。適温である21度前後を保つのは案外難しいんです」と話します。
昨年は暖冬の影響で、色づきばかりが早く、肝心の甘みや香りが乗るのに時間がかかり出荷が一ヶ月ほど遅れてしまいましたが、今年は順調とのことです。
ちなみに、日野市には5、6軒のイチゴ生産農家がいますが、「高設栽培」で手がけているのは篠崎さんともうお一人のみ。
身体への負担が軽減され、効率よく収穫できるというメリットがあります。
さらに、イチゴにはすのこを敷いて軸が折れないよう工夫も。これは、生育途中で軸が折れてしまうことで栄養が行き届かず、色づいても味が乗らないイチゴになってしまうことを防ぐために行います。
温度を丁寧に管理しゆっくりと時間をかけて色づかせ、香りが出るまで待って収穫するからこそ、納得のいくイチゴが生まれます。

待っている人たちのために
イチゴのハウス栽培について、「毎年同じようにやろうとしてもまったく同じイチゴができるということはない。だから今でも毎年勉強になるんです」と話す篠崎さん。
お客様から直接「今年も楽しみに待っているよ」という声が届くのも、栽培を続けていてよかったと感じる瞬間です。
おいしいイチゴは、上部まできれいに色がまわり、中の果肉は白いものがオススメだとか。

しゅんかしゅんかの店頭に並ぶ「とちおとめ」と「やよいひめ」は、手に取るだけでおいしそうな甘い香りを放ちます。
入荷は5月上旬ごろまで!ハウスの中で完熟する時を待ち収穫・出荷された地元のごちそうを、ぜひ味わってみてください。